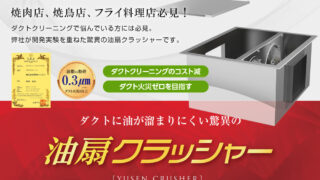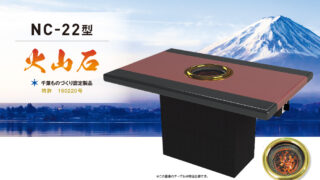冬は乾燥と換気量の低下が重なり、火災リスクが相対的に上がる季節です。室内の湿度が下がると可燃物は着火しやすく、静電気も発生しやすくなります。飲食店は調理用の火気と油脂を扱うため、乾燥期のリスク増は無視できません。まずは「乾燥=着火しやすい環境」を前提に、湿度管理や換気の確保を冬季運用の基本方針に置きましょう。
1. ダクト火災の典型パターンを知る
焼肉店や下引き/上引きダクトの無煙ロースタでは、火の付いた油や炎がダクトに吸い込まれ、内部に堆積した油かすに着火して延焼する事例が報告されています。厨房内からダクトへ延焼したケースや、オーブンや排気部からの発煙を起点とした事例も公表されています。これらは「ダクト内の油脂堆積」と「可燃性残渣への着火」が共通の要因です。
2. 冬場特有の運用リスク
乾燥による着火性の上昇:湿度低下で可燃物が乾き、静電気火花の発生もしやすくなるため、通常期より着火条件が緩くなる。加湿や帯電対策は冬季ほど重要。
換気量の低下:寒さ対策で開口部を閉めがちになる一方、厨房機器は繁忙期で稼働が増え、油煙負荷が高まる。排気系の性能低下(堆積)と相まって過熱・引火リスクが増す。
※この点は各消防のガイドラインでも「排気ダクト等の附属設備の適切な維持管理不足は危険」と明記。
ピーク時間帯の連続稼働:清掃間隔が延びたり、フィルター差し替えが後手になると、堆積ペースが速い冬は一気に危険域へ到達しやすい。
3. グリスフィルターの選定と清掃:最低限の基準理解
公表資料では、グリスフィルターの材料は「特定不燃材料」で、非着火性・耐熱性の試験基準に適合することが求められます。形状・材質により捕集性能が異なるため、厨房の油煙負荷に応じた仕様選定と、清掃を前提とした運用が不可欠です。
厚生労働省の基準でも、厨房ダクト・フード・グリスフィルターは随時点検し、油脂や汚れを十分に除去すること、ダクト内部も可能な限り清掃することが示されています。頻度は負荷に左右されますが、「見た目で汚れていない」に依存せず、時間基準+差圧や重量などの客観指標で運用すると冬期もブレにくくなります。
4. 冬季の清掃・点検スケジュール例(目安)
※設備・負荷・営業時間で変わるため、以下は考え方の例です。
毎日(営業終了時):フィルター表面の粗清掃/油受けの排油・洗浄/可視部の油滴や焦げ跡の確認。異常加熱・異臭があれば原因切り分け。
週1〜数回:フィルターを取り外して洗浄(アルカリ洗浄や高圧洗浄など店内手順に従う)。フード内部の油溜まり、照明カバーの油膜除去。
月1〜数回:ダクト内部の点検(点検口から堆積厚さ・付着状況を確認)。必要に応じ専門清掃を手配。冬は堆積ペースが上がりやすい店舗で短縮。
季節前(秋)/繁忙期中間:排気ファンの振動・異音・電流値の確認、ダンパー作動、ベルト張り、漏油や異常温度の兆候確認。
5. ダクト構造・材料・設置の基本
排気ダクトはステンレス鋼板等の特定不燃材料を用い、たわみ継手やグリスフィルターも耐熱性を備えた材料が求められます。上引きダクトについては火災発生が一定数報告され、位置・構造・維持管理の全国統一基準の必要性が議論されています。既存店は特に「居抜き由来の配置」や熱源近傍のダクト位置に注意し、可燃物や天井材との離隔、点検口の設置、清掃性の確保を優先しましょう。
6. 運用ルール:ヒューマンエラーを減らす
消防のガイドラインでは、飲食店火災の約半数が厨房設備等からの出火で、原因の多くが「加熱中の放置」です。「火から離れない」「離れる際は消火・消炎」を徹底。閉店前には、火気遮断・ガス遮断・ブレーカー操作のダブルチェック表を運用します。冬は暖房や加湿器の電源系も増えるため、回路過負荷の確認も忘れずに。
7. 無煙ロースタと下引き/上引きダクトの注意点
下引き:油が炎を伴って下方へ吸われ、ダクト内堆積物に着火した事例がある。火種(脂の発火)を起こさない焼成管理と、焼台〜ダクトまでの清掃性を重視。
上引き:都市部での火災発生が一定数あり、位置・構造・維持管理の明確化が課題。グリス捕集→排気までの連続系で弱点がないかを点検。
8. もしもの時の初動と避難
実際の事例では、多数の利用客を迅速に避難誘導したことで人的被害を抑えたケースがあります。
初期消火(不活性ガス・泡等の適合消火器の配置と訓練)→ 通報 → 避難誘導の順で役割を定め、訓練で煙の流れとダクト経路を理解しておくと初動が早くなります。
9. 冬に強い「点検・清掃・運用」チェックリスト(抜粋)
1. 湿度40〜60%目安の維持(静電気対策にも有効)。
2. フィルターの交換・洗浄周期を冬季短縮(負荷増・乾燥を考慮)。
3. ダクト内部の点検口活用:堆積厚や焦げ跡の有無を記録。
4. 閉店ルーティン:火気遮断・ガス遮断・電源遮断のダブルチェック。
5. 装置の材質・構造の再確認:特定不燃材料・耐熱性・非着火性の適合。
6. 上/下引きのリスク差に応じた訓練:焼台→フィルター→ダクトの連続性を理解。
10. 最低限おさえる法令・指針の読みどころ
厨房設備の火災予防ガイドライン:従業員教育と「排気ダクト等の点検・清掃」の具体的要領。冬季の運用強化にも直結。
グリスフィルター等の材料・試験適合:非着火・耐熱の基準と材質要件。更新や設備見直し時の根拠に。
清掃基準:ダクト・フード・グリスフィルターの随時点検と十分な除去、内部清掃の必要性。
火気器具と排気システムの安全措置:下方排気方式での油脂対策・逆流防止・ガス遮断など運用面の留意点。
冬は乾燥×換気低下×稼働増が重なる季節。ダクト火災の多くは油脂堆積と着火が引き金で、グリスフィルターの適切な選定と清掃の前倒し運用、ダクト内部の定期点検、火気の不放置が実効策です。公的ガイドラインと清掃基準を根拠に、季節変動を織り込んだ保守計画へ切り替えて、繁忙期を安全に乗り切りましょう。
(参考:各節の根拠は東京消防庁の公表資料、厚生労働省の清掃基準、消防庁関連資料、乾燥期の火災リスクに関する技術解説等に基づいています。)
排気設備や油煙対策の改善を検討されている方は、厨房環境や店舗条件に合わせた適切な提案ができる専門業者への相談がおすすめです。株式会社野田ハッピーでは、飲食店の換気・防火・脱臭設備に関するご相談を承っております。現場の状況に応じた安全で経済的な対策をお考えの方は、下記リンクより詳細をご覧ください。
⇒ 株式会社野田ハッピー 公式サイトはこちら